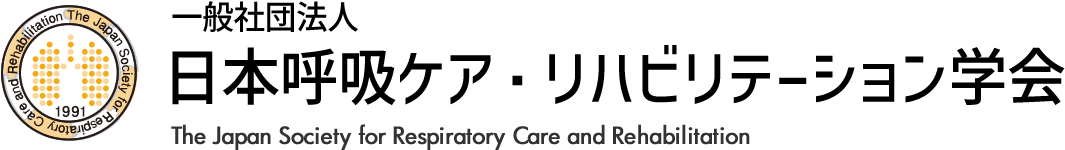各委員会 / 呼吸不全緩和ケア検討委員会
非がん性呼吸器疾患に対する緩和ケアの重要性について
日本呼吸ケア・リハビリテーション学会
近年、慢性閉塞性肺疾患(COPD)や間質性肺炎、気管支拡張症などの非がん性呼吸器疾患により、長期にわたり呼吸困難や生活の質(QOL)の低下に悩まされる患者さんが増加しています。これらの疾患は、進行とともに症状が重くなる一方で、緩和ケアの必要性が十分に認知されていない現状があります。
日本呼吸ケア・リハビリテーション学会は、非がん性呼吸器疾患を抱えるすべての方が、その人らしく、尊厳を持って生活を送れるよう支援することが重要であると考えています。
緩和ケアは「人生の最終段階の医療」にとどまりません
「緩和ケア」と聞くと、がんの終末期医療を連想される方が多いかもしれません。しかし本来、緩和ケアとは病気の早期から、つらい症状や精神的な負担をやわらげるための支援を意味します。
COPDや間質性肺炎などの非がん性呼吸器疾患においても、呼吸困難、不安、倦怠感、孤独感など、さまざまな苦痛があります。こうした症状に寄り添い、適切な緩和ケアを行うことは、より良い日常生活を送るために不可欠な支援です。
私たちが伝えたい3つのこと
- どの段階でも緩和ケアは受けられます
非がん性呼吸器疾患は長期間にわたる疾患です。病気の進行度にかかわらず、症状緩和や生活のサポートを目的としたケアを早い段階から受けることができます。 - 医療・看護・リハビリ・福祉が連携します
医師、看護師、理学療法士、作業療法士、管理栄養士、薬剤師、公認心理師、ソーシャルワーカーなど多職種が連携し、患者さんの生活の質を支える体制を整えています。 - 患者さんとご家族の「希望」に寄り添います
どのように生きたいか、どんな暮らしを大切にしたいか。緩和ケアは、患者さんとそのご家族の価値観や希望を尊重する医療です。
解決すべき3つの制度的課題
- 呼吸リハビリテーションの普及
専門医療機関に限らず、プライマリ・ケアの場でも早期から終末期まで、呼吸リハビリテーションが提供できる仕組みを整え、地域に根ざした支援体制を充実させる必要があります。 - 緩和ケアへのアクセス改善
診療報酬制度が主にがんを対象としている現状を改め、非がん疾患でも公平に緩和ケアを受けられる体制整備が必要です。 - 症状緩和におけるオピオイド使用の保険適用拡大
呼吸困難に対するオピオイドの有効性は明らかであり、安全な使用体制を前提に、非がん性呼吸器疾患にも保険適用を広げることが求められます。
私たちは、これらの課題解決に向け、国や関係機関への働きかけを強め、すべての患者さんが安心して暮らせる社会の実現を目指してまいります。
国民の皆様へ
呼吸器の病気を抱えていても、安心して暮らすための支援があります。どうか一人で悩まず、まずは医療者に相談してください。緩和ケアは「最後の手段」ではなく、「生きる力を支える支援」です。
私たち日本呼吸ケア・リハビリテーション学会は、すべての患者さんとご家族が、地域の中で安心して暮らせる社会の実現を目指し、今後も取り組みを続けてまいります。
2025年8月23日
一般社団法人日本呼吸ケア・リハビリテーション学会
理事長 黒澤 一
呼吸不全緩和ケア検討委員会委員長 津田 徹
診療報酬適正化委員会委員長 堀江 健夫